街道をゆく35 オランダ紀行 朝日文庫 ★★★★★
個人的には、オランダという国は、地球上でもっとも興味のない国の一つだった。重厚な歴史があるわけでもなく、そして何といっても、山がない。
私にとってのオランダのイメージといえば、運河と風車とチューリップ、という幼児レベルのものだった。
だが本書を読んで、なぜ今までオランダに興味を持てなかったか、わかったような気がした。
オランダは市民の国であり、商人の国であり、プロテスタントの国である。オランダ人とはオランダ国籍をもつ人にすぎず、バスク人やケルト人のような言語(オランダ語)へのこだわりもなく、国家としてのアイデンティティーが希薄なのだ。
むろん、オランダにも歴史はある。それどころか、小国ながら、世界史の主役に躍り出たこともある。オランダの黄金時代は、長くは続かなかったが。
そういう意味では、不思議な魅力を持つ国である。
そして言うまでもなく、オランダは日本史と深い関わりを持つ。
司馬遼太郎は、
国じゅうが暗箱の中に入って、針で突いたような穴が、長崎にだけあいていた。
そこから入るかすかな外光が、世界だった。
長崎の出島に"監禁"されていたオランダ人は、常時わずか十数人であった。その十数人が、二千数百万の人口の社会に多少の影響をあたえつづけたということは、日本人の好奇心という点からみても、文明史上の奇蹟だった。
と述べている。
かつて日本は、南蛮貿易を行っていた。しかし、カトリックのスペインは、神の名において、アメリカ大陸で暴虐の限りを尽くした。従って、秀吉がキリスト教を弾圧したのは懸命な判断だっただろう。
江戸幕府が、鎖国しながらもオランダ(と清)にだけ交易を許したのは、オランダがプロテスタントの国だったからだ。
でも、日本史におけるオランダの重要性に比べると、オランダ史における日本は影が薄い。つまり、両国の関係は非対称なのだ。ゴッホが浮世絵に影響を受けたことと、ライデン大学に日本語科があることくらいかもしれない。
司馬遼太郎が、「街道をゆく」の行き先としてオランダを選んだのは、もちろん日本史との関わりがあるからだろう。
実際、本作品は、福沢諭吉で始まり、最後のオランダ人教師だったボードインで終わっている。(ボードインの忠告がなければ、今ごろ上野の山は取りつぶされて、そこに東京大学が建てられていたところだった。)
けれども、江戸期の日本にまつわる話はそれほど多くない。
印象的だったのは、レンブラント、ルーベンス、ゴッホといった画家について話である(ただ不思議なことに、フェルメールの話はほとんど出てこない)。あまり「らしくない」話題なのだが、それが却って司馬遼太郎の博覧強記ぶりを示していて、実に面白いのだ。オランダ紀行も、司馬遼太郎の手にかかるとこうなるのか・・・と思った。
レンブラントは、司馬遼太郎をして「私は、あらゆる点で、レンブラントが、人類史上最高の画家の一人だったと思っている」と言わしめている。
本書に出てくる「夜警」はアムステルダムの国立美術館に、「トゥルプ教授の解剖学講義」はハーグのマウリッツハイス美術館に収蔵されている。(ちなみに「トゥルプ」とはチューリップのことである。)
司馬遼太郎は、隣国ベルギーにも足を伸ばしている。
オランダには、「世界一薄い本が、二つあるんです。一つはドイツ人のユーモアの本で、一つはベルギーの歴史の本です」というジョークがあるという。実際、ベルギーが独立したのは1830年で、オランダに輪をかけて歴史が薄っぺらい。
ルーベンスといえば、アントワープの聖母大聖堂にある「キリストの降架」である。そしてこの絵は、「フランダースの犬」で、ネロが死の直前にやっと見ることができた、あの絵なのである。
ネロと愛犬パトラッシュは、日本においては、「桃太郎か浦島太郎ほどの知名度でもって知られている」。ところが、本家のベルギーでは、この物語を知る人はほとんどいないというのだ。
それでも、あまりに多くの日本人が押しかけるものだから、「フランダースの犬」が観光資源として活用されるようになったという。日本から「逆輸入」されたわけである。
終盤、ゴッホの伝記も印象的だった。
私には、ゴッホの天才を判断することはできない。だが、絵画という世界において、生前まったく認められなかったにもかかわらず、死後何年も経ってから「天才」と崇められるようになった、という現象が起きたことは非常に興味深い。
認められなかった、どころではない。ゴッホは27歳にしてようやく画家を志し、ベルギーの王立美術学校に入学したものの、わずか一ヶ月で落第し、13歳か15歳の初心者クラスにおとされたという。そして、自身の耳を切り取って、娼婦にプレゼントとして渡した挙げ句、失意の内に自殺した。
ゴッホの唯一の理解者として送金しつづけた弟のテオは、ゴッホの後を追って半年後に自殺する。残されたテオの妻、ヨハンナが、ゴッホの絵画や書簡を整理して保管しておかなかったら、画家ゴッホはこの世に存在しなかったのである。
本書に登場する「馬鈴薯を食べる人々」も、有名な「ひまわり」も、アムステルダムのゴッホ美術館にある。
先日、飛行機の乗り継ぎ時間を利用して、初めてアムステルダムを訪れた。そのときは滞在時間が数時間しかなかったため、美術館は完全にスルーした(そもそも興味もなかった)。
だがもし、再び訪れる機会があるならば、是非とも実物を見てみたいと思う。
(なお、ゴッホの「ひまわり」は、新宿の損保ジャパン日本興亜美術館でも見ることができる。これは、バブル期まっただ中の1987年に(当時の)安田火災海上保険が53億円で落札したもので、金満ニッポンを象徴する出来事だった。)(19/09/10読了 19/09/16更新)
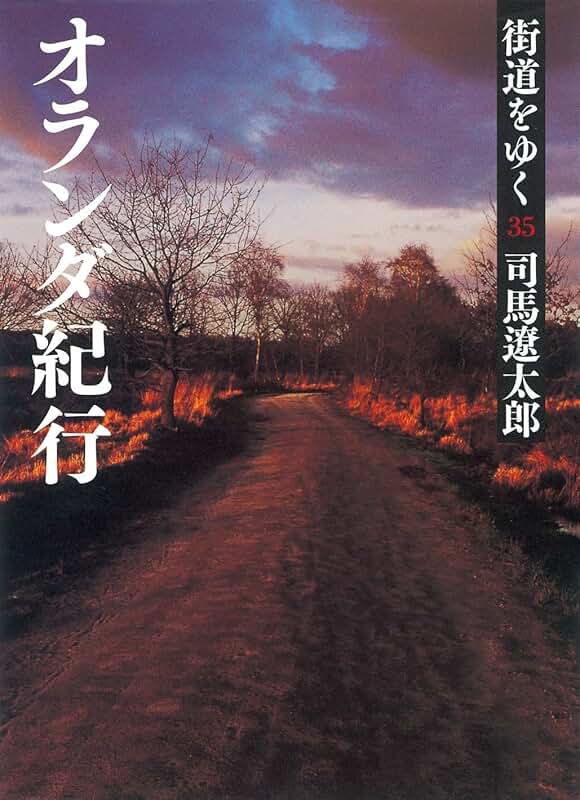
 読書日記 2019年
読書日記 2019年 