日韓 理解への道 ★★★★☆ 鮮于輝・高柄翊・金達寿・森浩一・司馬遼太郎 中公文庫
本書は、1982年(昭和57年)に行われた座談会を書き起こしたものである。
このうち3人は韓国(朝鮮)人である。参加者は、森浩一氏を除き、1919年〜1924年の生まれだ。
この時はまだ戦後37年しか経っていなかったから、韓国には、日帝時代の忌まわしい記憶が濃厚に残っていただろう。
これは、そういう時代に、日本語での教育を強要された人たちが、侵略者の言語である日本語で、日本について語るというセンシティブな企画だった。その点がまず注目に値する。
この時代、日本は世界第二の経済大国の地位を不動のものにし、飛ぶ鳥をも落とす勢いだった。
司馬さんは、日中韓の東アジア三カ国を「三軒長屋」などと称しているが、今にして思えば、ずいぶん牧歌的な時代だった。今、司馬さんが生きていたら、現在の世界情勢をどう評するだろうか。
一方の韓国はといえば、南北の分断はますます固定化されるばかり。昔も今も、このことが発展への巨大な足枷になっていることを思うと、気の毒としか言いようがない。
日韓のつながりを考える上でもっとも興味深いのは、文献記録があまり残っていない古代だろう。
百済・新羅・高句麗が並び立っていた三国時代、朝鮮半島から日本列島に続々と人々が渡ってきた。特に、百済滅亡の際には、王族が丸ごと移住してきた。すると、日本語というのは、百済語の末裔なのだろうか。
あるいは、東京には狛江市があるが、この「こま」は高麗(高句驪)のことだという。さらに、奈良は韓国語で「くに」を表すナラ(나라)から来ているというが、本当だろうか。
いずれにせよ、日本人はほとんど──といっては言い過ぎだが、かなりの程度、韓国人なのである。
もちろん、当時から日本列島には、土着の縄文人・弥生人が住んでいた。だが不思議なことに、日本列島から朝鮮半島への逆向きの移住は、ほとんどなかったようなのだ。
それから、かつて学校で「任那日本府」というのを習ったが、これは多分にイデオロギッシュな概念で、そんなものはそもそも存在しなかったと考えられているようだ。
司馬さんは、「朝鮮半島」(韓国語では「韓半島」)全域を指す適切な呼称がないことを嘆いている。
本書でも触れられているが、NHKの「ハングル講座」というタイトルは、Korean languageを「韓国語」とするか「朝鮮語」とするかという問題を回避するための、苦し紛れの策だった(ハングルは文字であって言語名ではないから、これは奇妙なタイトルである)。
現在では「韓国語」が定着した感があるが、かつては「朝鮮語」に加えて「韓国・朝鮮語」、「コリア語」といった珍妙な呼称も使われていた。東京外大や大阪外大(現・阪大)では、今なお頑なに「朝鮮語」の呼称を使い続けている。(25/10/04読了 25/10/09更新)
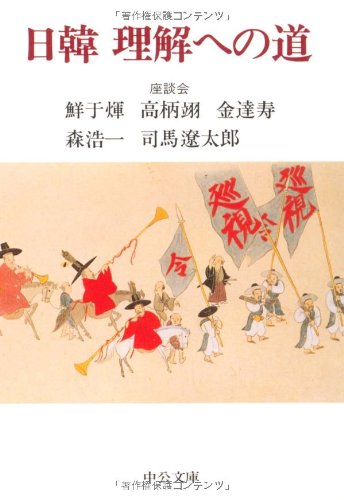
 読書日記 2025年
読書日記 2025年 